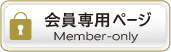金襴の由来
金襴の製造は、中国の宋代(10世紀~12世紀)に金箔糸を織り込む技術が編み出され、明代(14世紀~17世紀)に全盛期を迎えました。 金襴の名称の起りは判然としませんが、元代(13世紀~14世紀)の《事林歴記》官民服飾の条に「四品五品金袖襴」とあり、これが袖と襴(衣の裾につく襞)に金文のある衣服と解釈されることや、道元の著 《正法眼蔵(1231~53)転法輪》に「たとひ金襴衣なりとも、仏祖すでに拈来すれば仏法輪なり」とあり、この頃には金糸が入った袈裟を金襴衣(きんらんえ)と認識されており、金糸入りの襴衣の名が転じて織物の名称として用いられているようになったと思われます。(世界大百科事典・コトバンクより)
日本には、鎌倉時代に入宋の禅僧が伝法印可のしるしとして授けられた袈裟や書画の付属品として持ち込まれ、室町時代には朝貢の返礼として、また交易品として盛んに舶載されるようになりました。 国内で初めて織られたのは、天正年間(1573~92)に大阪堺にて明の職工の指導のもとこの種の技法が伝えられ、のちに京都西陣で盛んに織られるようになりました。 それらのうちで茶道の仕覆(しふく)や軸物の表装などに用いられていたものが名物裂として珍重され、今日に伝えられています。 そうした金襴は能装束、袈裟、帯、装飾用布地、人形衣装着など様々な用途に用いられるようになり今日に至ります。